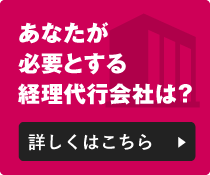電子帳簿保存法の法改正で何が変わるのか?
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。会社法や法人税法などで保存が義務付けられている帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿書類について、紙文書での保存ではなく、電子データでの対応を認めた法律です。
これまでの紙文書で保存する方法は紙や印刷代、保存用ファイルなどのコストがかかるほか、整理作業や保管のためのスペースの確保などの負担が経理業務において長年の課題となっていました。電子データであれば紙の原本が不要になり、印刷コストの削減や保管業務への負担の軽減など、これまで抱えていた課題を解決へと導くポイントがつまっています。
経理業務において電子帳簿保存法がもたらすメリットは大きかったものの、1998年の施行当初は電子帳簿保存法の適用要件が厳しかったこともあり、導入する企業は多くありませんでした。それを受けて電子データでの保存が認められる対象を拡大したり、スキャンによるデータの保存が可能になったり、デジタルカメラやスマートフォンで撮影したデータも有効とされたり、と時代に合わせて法改正が何度か行なわれています。
さらに多くの企業が紙文書の電子データ化に踏み出せるように2021年度(令和3年度)の税制改正で電子帳簿保存法の抜本的な見直しが行なわれたのが、2022年1月から施行が開始される新しい電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法の法改正ポイント
2021年の税改正で見直しが行なわれた電子帳簿保存法改正のポイントは次の4つです。
- 承認制度の廃止
- タイムスタンプ要件の緩和
- 適正事務処理要件の廃止
- 検索要件の緩和
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
承認制度の廃止
法改正前は電子帳簿保存法を導入する月の3ヶ月前までに、所轄の税務署に申請書を提出して承認を得る必要がありました。承認申請書の準備にかかる手間や承認までの待機時間の長さから導入をためらう企業が多かったこともあり、承認制度が見直されることに。その結果、改正後は承認自体が不要になり、電子帳簿保存法に対応した機能を備えているスキャナや会計システムなどの準備が整い次第、電子帳簿保存法を導入できるようになりました。
タイムスタンプ要件の緩和
従来は国税関係書類をスキャナ読み取りした際は、受領者が自署したうえで3営業日以内のタイムスタンプの付与が必須でした。今回の法改正により、受領者の自署が不要になったほか、タイムスタンプ付与の期限も3営業日以内から最長2ヶ月に延長されることに。受領者が自署する手間がなくなったほか、タイムスタンプの付与期間が大幅に延長されたことで担当者が余裕をもって紙文書の電子データ化を進められるようになります。
適正事務処理要件の廃止
適正事務処理要件とは、不正防止として社内規定の整備を目的としたものです。そのため、これまでの電子データに関する事務処理には「相互けん制」「定期的な検査」などの決まりが設けられていました。相互けん制とは、電子データ化の作業には2人以上で対応しなければいけないもの。作業を相互チェックすることで、不正が起きないようにという目的があります。
定期的な検査は、電子データ保存後に改ざんなどの不正がないかを確認するためのもので、これまでは検査のために電子データ化後も紙文書の原本を保管しておく必要がありました。それが法改正により適正事務処理要件が廃止されたことで、改正後は1人で電子データ化の作業ができ、原本の即時廃棄も可能となっています。
検索要件の緩和
検索要件とは、作成した電子データを検索するために設ける項目のことです。電子データの保存には、取引年月日をはじめ、勘定科目や取引金額、さらにその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索できる機能が必須となっています。これまでの電子帳簿保存法では記録項目の範囲を指定したり、項目を組み合わせて設定できたりする機能の確保が求められ、要件の複雑さから企業が導入をためらう要因の1つとなっていました。
それが法改正によって、検索要件が取引年月日、金額、取引先のみに簡素化。さらに、保存義務者が国税庁などの要求により電子データのダウンロードに応じる場合は、要件を複雑化させていた範囲指定や項目を組み合わせて設定する機能の確保が不要になりました。
経理代行サービスといっても代行会社によって対応範囲は様々です。自社対応と経理代行サービスのどちらがコストメリットやリスク管理につながるかを比較しながら、サービスの利用を検討してみるのをおすすめします。
ここでは、おすすめの経理代行会社の経理業務のサポート範囲を比較しているので、依頼を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
電子帳簿保存法改正で注意すべきポイント
電子帳簿保存法の抜本的な見直しにより制度や要件が廃止または緩和されたことで、これまで導入をためらっていた企業でも電子帳簿保存法に踏み出しやすくなりました。一方で、今回の法改正によって留意すべきことが2点あります。それが「罰則規定の新設」と「電子取引データの書面保存の廃止」です。
特に電子取引データの書面保存の廃止は、これまで電子帳簿保存法を導入していなかった企業にも関係あるため、しっかりと理解しておきましょう。
罰則規定の新設
電子データ化したPDFファイルなどのエビデンスを改ざんするなどして不正計算を行なった場合、重加算税が課されます。これまでも罰則規定として35%の重加算税が設けられていましたが、法改正によりさらに10%が加重され、今後は合計45%もの重加算税が課されることに。当然ながら不正を行なわなければ何の関係もない規定ですが、改めて認識しておく必要があります。
電子取引データの書面保存の廃止
従来の電子帳簿保存法では、取引先からメールなどで添付されて送られてきた請求書のPDFファイルやEDIシステムで授受されたデータなどは、紙に出力して保存する代替処置が認められていました。税務署に電子帳簿保存法の導入を申請していない企業でも電子データの書面保存がこれまで認められていましたが、今回の法改正により認容規定が廃止。
すべての企業において、取引先から送られてきた請求書のPDFファイルやEDIシステムで授受されたデータなどは、法令要件に従って電子データでの管理が求められるようになりました。そのため、たとえこれまで通りに紙に出力して書面保存したとしても、原本としては認められません。従って、今後は以下の対応のうちいずれかを選択して実行する必要があります。
- 電子データでもらっていたエビデンスを今後は取引先から紙文書でもらう
- PDFファイルにタイムスタンプを付与してから送信してもらう
- メールで送られてきたPDFファイルを授受後、最長2ヶ月以内に自社でタイムスタンプを押す
- PDFファイルの修正・削除ができないシステムを利用して授受・保存する仕組みにする
(修正・削除のログを記録できるシステムでも可) - 「正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規定」の策定・運用・備付を行なう
電子帳簿保存法改正により電子取引に関するさまざまな要件が変更されたため、2022年1月の施行開始に向けて今の運用で要件を満たしているかの確認や見直しが必要になります。または新たに導入するにあたって、要件を満たしたうえで円滑な運用ができるように準備しておきましょう。
経理代行なら導入や運用にかかる手間が不要
電子帳簿保存法の改正により導入しやすくなったものの、定められた要件の把握や自社のシステムの確認、さらに円滑な運用のための人材教育やシステムの構築などが必要になります。従来の経理業務と並行しながら電子帳簿保存法の導入に向けて対応するのは経理担当者の業務負担が大きくなり、離職リスクにつながりかねません。
新しくなる電子帳簿保存法に対応可能な経理代行であれば、スムーズな導入や運用が可能です。タイムスタンプやスキャンの代行作業など電子データ化するための面倒な作業を代行できれば、経理担当者の負担も軽減され、離職リスクも回避できるメリットがあります。
経理代行といっても代行会社によって対応範囲は様々です。
ここでは、多岐にわたる経理業務の対応・サポートができる経理代行会社3社をピックアップ。各社の対応可能範囲をまとめました。
経理業務を丸投げ
月5万円~依頼できる
経理の特命レスキュー隊

引用元:経理の特命レスキュー隊株式会社公式HP
(https://www.accounting-rescue.com/)
税理士や日商簿記検定1級などの会計資格を持った隊員が、経理業務をまるっとサポート。
一部業務のみを代行
記帳代行だけでも依頼できる
経理外注・記帳代行センター

引用元:経理外注・記帳代行センター公式HP(https://www.tokyo-keiri.com/)
記帳代行や年末調整代行、給与計算代行のみなど、スポットで依頼できるのが特徴。
経理業務フローを改善
体制から見直してくれる
TOKYO経理サポート

引用元:TOKYO経理サポート公式HP
(https://anshin-keiri.eiwa-gr.jp/)
事業内容に沿った経理業務フローの改善提案といった、コンサルティングも行うのが強み。