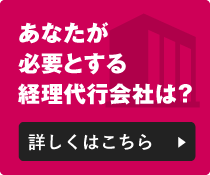知っておきたいIFRS(国際会計基準)の基礎知識
IFRS(国際会計基準)とは?
IFRS(International Financial Reporting Standards)とは、国際会計基準審議会(IASB)が世界共通の会計基準を目指して策定したものです。120ヶ国以上がIFRSを採用しており、EU(欧州連合)においては上場企業に関してIFRSの適用が義務付けられています。
日本でもIFRSに基づく収益認識基準が適用開始
世界で広がりを見せているIFRSですが、日本ではこれまで任意適用にとどまっていました。けれど、2021年4月以降の事業年度からIFRSを踏まえた「収益認識に関する会計基準」(収益認識基準)の適用が開始され、公認会計士の会計監査を受ける企業をはじめ、上場企業や大企業などは強制適用の対象となっています。
未上場の中小企業は任意適用のため、これまで通りの会計基準で問題ありません。ただし、取引先に収益認識基準を適用している企業がある場合、契約の結び方が収益認識基準に沿ったものに変更になる可能性があります。そのため、任意適用の中小企業においても、IFRSや収益認識基準の大まかな内容だけでも把握しておいて損はありません。
日本会計基準とIFRSの違い
日本会計基準とIFRSの違いはいくつかありますが、ここでは「財務報告のルール」「利益の考え方」「のれんの償却方法」の3つの違いについて解説します。
財務報告のルール
財務報告のルールにおいて、IFRSは原則主義を採用しています。原則主義とは詳細な規定や数値基準を設けない会計主義を指し、運用や解釈を企業任せにする自由度の高さが特徴。ただし、解釈の根拠を外部に明示しなければいけないため、大量の注記が必要になります。一方で、日本会計基準では細則主義を採用。自由度の高い原則主義と違い、細則主義には実務指針や数値基準など細かい規定が定められており、ルールに基づいた運用が求められます。
利益の考え方
IFRSでは貸借対照表を重視する資産負債アプローチを採用しており、企業のすべての財産からマイナス要素を差し引いた純資産を利益とする考え方です。日本の会計基準の場合は企業の一定期間の収益から費用を差し引いた純利益を利益とする考え方で、損益計算書を重視する収益費用アプローチを採用しています。
資産負債アプローチは投資家や債権者が知りたい企業価値を明確にすることを目的としており、一定期間での期首の残高と期末の残高を比較することで企業の存続力や成長力がどのぐらいあるのかを示すことができます。収益費用アプローチの目的は、企業の収益力を明確にすること。一会計期間に区切って算出された純利益により、その企業がどれだけの収益獲得能力があるのかを判断できます。
のれんの償却方法
のれんとは、ある企業を買収した際の買取価格がその企業の純資産を上回る額のことをいいます。たとえば純資産が1億円の企業を3億円で買収した場合、差額の2億円がのれんとして計上されるというわけです。日本会計基準とIFRSではのれんの償却方法に大きな違いがあり、見かけ上の利益が大きく変わる可能性があります。
日本会計基準ではのれんは20年以内の償却が定められており、のれんの償却が終わるまで費用として毎年計上しなければいけません。そのため、巨額の買収を行なった場合はのれん代以上の利益を出さなければ営業赤字に見えてしまい、利益成長が求められる上場企業にとってはのれんの償却費が大きな負担となります。
一方で、IFRSではのれんの規則的な償却が行なわれません。代わりに、のれんの価値が著しく下落した際に減損処理が行われます。減損処理とは、資産の収益性が低下したことなどの理由で投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件に従って帳簿価額を減額する処理のことです。
毎年のれんの価値を評価する減損テストを実施し、期待通りの収益をあげていればのれんが費用に計上されることはありません。IFRSであればのれんの償却費によって収益が削られる心配がないため、見かけ上の営業利益が大きくなります。
実際に日本たばこ産業(JT)が2012年3月期からIFRSを導入したところ、のれんの償却額が約800億円減少し、営業利益が前年同期より約724億円アップと大幅に上昇する結果となりました。
経理代行サービスといっても代行会社によって対応範囲は様々です。自社対応と経理代行サービスのどちらがコストメリットやリスク管理につながるかを比較しながら、サービスの利用を検討してみるのをおすすめします。
ここでは、おすすめの経理代行会社の経理業務のサポート範囲を比較しているので、依頼を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
IFRSを導入するメリット
海外企業に業績や企業価値を伝えやすい
利益の考え方が違う日本会計基準だと海外の投資家やアナリストが企業の財務状況や企業価値を評価しづらく、海外からの資金調達を受けにくくなる可能性があります。世界で大きな広がりを見せている国際会計基準のIFRSであれば、海外の投資家やアナリストが海外企業の財務諸表と横並びで比較できるため、自社の業績や企業価値を評価してもらいやすくなります。
経営管理に役立つ
海外に子会社を持っている企業の場合、子会社と同じIFRSを導入することで勘定科目の階層やシステム方針が統一化され、経営管理がしやすいメリットがあります。また、子会社の財務状況を把握するために、日本の会計基準に変換する手間もかかりません。会計基準の方針が統一化により子会社との連携が強化され、スムーズかつスピーディーな意思決定が可能になります。
IFRSを導入するデメリット
経理の事務負担が増える
日本の会社法上では日本基準での開示が求められるため、IFRS用と日本会計基準用の複数帳簿を完備しなければいけません。また、IFRSの原則主義により大量の注記が必要になるので、経理での事務負担が増加するデメリットがあります。
導入にコストがかかる
IFRSはこれまでの日本会計基準と大きく異なるため、外部アドバイザーや監査関連の報酬をはじめ、システム変更に伴うコストの増加、従業員への教育など、導入するにあたってさまざまなコストが必要になります。メリットやデメリットを含めて企業に大きく影響を与えるので、導入を検討する際は総合的に判断し、綿密な計画を立てたうえで進めていきましょう。
自社内での対応が難しいならアウトソーシングが吉
日本でもIFRSに基づく収益認識基準の適用が開始され、経営者や経理担当者は従来の会計基準のほかにIFRSについても把握しておく必要があります。IFRSの導入により海外企業から資金調達を受けやすい、経営管理に役立つといったメリットはあるものの、やはり気になるのが導入に伴う事務負担やコストの増加です。
現在の自社のシステムや人材では対応が難しい、もしくはかなりの時間やコストを要するといった場合に検討したいのが経理代行サービスの利用。IFRSや収益認識基準に対応している経理代行サービスであれば、サービスの利用にコストはかかるものの、経理事務の負担増加や従業員への教育、システムの変更を避けられ、IFRSや収益認識基準の円滑な運用が可能です。
経理代行といっても代行会社によって対応範囲は様々です。
ここでは、多岐にわたる経理業務の対応・サポートができる経理代行会社3社をピックアップ。各社の対応可能範囲をまとめました。
経理業務を丸投げ
月5万円~依頼できる
経理の特命レスキュー隊

引用元:経理の特命レスキュー隊株式会社公式HP
(https://www.accounting-rescue.com/)
税理士や日商簿記検定1級などの会計資格を持った隊員が、経理業務をまるっとサポート。
一部業務のみを代行
記帳代行だけでも依頼できる
経理外注・記帳代行センター

引用元:経理外注・記帳代行センター公式HP(https://www.tokyo-keiri.com/)
記帳代行や年末調整代行、給与計算代行のみなど、スポットで依頼できるのが特徴。
経理業務フローを改善
体制から見直してくれる
TOKYO経理サポート

引用元:TOKYO経理サポート公式HP
(https://anshin-keiri.eiwa-gr.jp/)
事業内容に沿った経理業務フローの改善提案といった、コンサルティングも行うのが強み。