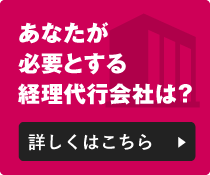経理の年間スケジュールについて
経理業務の年間スケジュールを把握する
経理部門の業務にはさまざまなものがあります。そのため、年間スケジュールを把握しておくことは必須だといえるでしょう。こちらでは、経理の年間スケジュールについて、月次でどのような業務をこなす必要があるのかを詳しく紹介しています。
日次業務・月次業務・年次業務
経理の年間スケジュールで重要なのが、「日次業務・月次業務・年次業務」の把握です。「日次業務」は、現金の入出金や残高、立替経費の精算や伝票整理、記帳業務があたります。
「月次業務」は、月次決算をはじめ、得意先への請求書発行と代金回収、急の支払いや仕入先への支払いなどです。一般的に1ヶ月~3ヶ月分を月次業務として処理します。
「年次業務」は、1年に1度だけある決算業務です。経理にとっていちばん大事な業務で、決算整理・決算書作成・確定申告書の作成や納税までを対応します。そのほか、社会保険や労働保険関連、年末調整や給与支払報告書をまとめるなどの重要な業務もありますので、年間スケジュールを把握しておくことは必須だといえるでしょう。
決算月は3月・9月・12月が多い
一般的に多くの企業が決算期を3月に設けています。理由として国の公共機関が3月を会計年度にしており、企業で行う決算もこの時期に合わせているためです。また、法律改正が適用されるのは4月1日が多く仕訳方法への影響を減らしたいといった理由で、3月決算にしている場合もあります。
そのほか、決算期を9月に設けている企業が多いのは、3月だと監査法人や税理士が忙しく、4月は人事異動も多くなるためにずらしたいという理由があるようです。一部の企業では3月や9月ではなく、12月に決算を行う企業もあります。12月に決算を行う企業は、単純に暦に合わせて決算を行っているということが考えられますが、グローバル化による国際基準に合わせる形にしている企業もあるようです。
1月~3月は実地棚卸などがあり忙しい
1月には、固定資産税の償却資産に関する申告や源泉所得税の納付、法定調書・給与支払報告書の提出、支払調書の作成・提出があります。2月には、固定資産税や都市計画税の納付が多くの企業で行われます。また、決算業務が迫るために決算計画の作成や部門への協力依頼を行うことが多いようです。
3月には、決算を行う前に残高を明確にする実地棚卸があります。実地棚卸は、4月の決算整理にも関わるため重要です。
4月は決算整理
3月決算の企業では4月が年度初めになるため、年間スケジュールの中でも忙しくなる時期です。棚卸しで把握した在庫と帳簿残高の確認、差額の調整などを実施。年度中に把握できていない入出金があれば原因を調査して会計処理を行います。また、減価償却費の計上や各勘定科目の経理処理を見直すのも重要業務のひとつです。
決算整理の内容に基づき、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書といった決算書の作成を行います。固定資産税や都市計画税の第1期分の支払いが必要です。
5月は法人住民税の確定申告・納付
5月には法人税や法人住民税、法人事業税や消費税の確定申告と納付があります。法人税や消費税は期末から2ヶ月以内に確定申告をし、税務署に納税しなければなりません。法人住民税や法人事業税に関しても、期末から2ヶ月以内の申告と納付が求められます。
そのほか、6月に行われる株主総会の準備も必要です。株主に開催一週間前までに通知をし、決算説明資料の準備を進めます。
6月は株主総会や個人住民税の納付
6月には株主総会を開催します。株主に売上高や利益など、決算数値を報告しなければなりません。また、個人住民税の納付も6月にあり、納期の特例の適用を受けているのであれば、決められた期日までに社員から徴収した個人住民税を納付する必要があります。
7月は源泉所得税の納付や健康保険・厚生年金保険の定時決定
納期の特例の適用を受けている場合、徴収した1月~6月分の源泉所得税を決められた期日までに納付する必要があります。あわせて固定資産税も7月に納付。そのほか、健康保険や厚生年金保険の定時決定では、決められた期日までに従業員の社会保険料の合計額を日本年金機構に提出します。
8月~11月はリフレッシュ期間
8月~10月は中期報告が中心となり、1年を通していちばん落ち着く期間になります。大規模事業者は、8月に消費税の四半期中間申告と納付を実施。11月は法人税や法人事業税や消費税の中間申告を行います。
12月は決算に向けての準備期間
12月は決算に向けての準備期間です。支払った所得税の中で過不足を調整、固定資産税を納付します。納期の特例の適用を受けているなら、決められた期日までに個人住民税の納付です。
年間を通して多忙な経理担当者ですが、その中でも繁忙期が存在します。現状の人数では経理の負担が大きい企業も多いのではないでしょうか。
そのような場合は、経理業務を代行業者に委託するのがおすすめ。通年や、特に忙しい時期だけなど、代行業者によって依頼できる期間もさまざまです。
ここでは、おすすめの経理代行業者の対応範囲を比較しています。経理担当者の負担軽減のためにも、アウトソーシングの検討を進めてみてください。
経理部門では年間を通して多くの業務がある
経理の業務は8月~11月は落ち着いているものの、年間を通して多くの業務があります。スケジュールを把握しておけば、スムーズに業務が行えるため、精神的にも余裕を持って対応できるでしょう。
追い詰められて、これもあれもしなければならないとパニックになればミスも多くなります。そうならないよう、年間スケジュールを頭に叩き込み、万全の体制を整えておきましょう。
経理代行といっても代行会社によって対応範囲は様々です。
ここでは、多岐にわたる経理業務の対応・サポートができる経理代行会社3社をピックアップ。各社の対応可能範囲をまとめました。
経理業務を丸投げ
月5万円~依頼できる
経理の特命レスキュー隊

引用元:経理の特命レスキュー隊株式会社公式HP
(https://www.accounting-rescue.com/)
税理士や日商簿記検定1級などの会計資格を持った隊員が、経理業務をまるっとサポート。
一部業務のみを代行
記帳代行だけでも依頼できる
経理外注・記帳代行センター

引用元:経理外注・記帳代行センター公式HP(https://www.tokyo-keiri.com/)
記帳代行や年末調整代行、給与計算代行のみなど、スポットで依頼できるのが特徴。
経理業務フローを改善
体制から見直してくれる
TOKYO経理サポート

引用元:TOKYO経理サポート公式HP
(https://anshin-keiri.eiwa-gr.jp/)
事業内容に沿った経理業務フローの改善提案といった、コンサルティングも行うのが強み。